近年、健康志向の高まりから注目を集めている米粉パン。
しかし、米粉パンには乳製品が含まれている場合も多々あります。
乳製品不耐症や乳製品アレルギーを持つ方にとっては注意が必要です。
そこで今回の記事では、乳製品不耐症と乳製品アレルギーの違いについて原因、症状、対処法などを詳しく解説します。
乳製品不耐症とは?

乳製品不耐症は、小腸で乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低いことが原因で起こります。
ラクターゼの活性が低いと、腸内未消化の乳糖が腸内細菌によって分解され、ガスや下痢などの症状を引き起こします。
原因

乳製品不耐症は、主に以下の原因で起こります。
- 遺伝的要因: 乳糖不耐症は、遺伝的な要素が強いと言われています。両親どちらか、または両方が乳製品不耐症の場合、乳製品不耐症を発症する可能性が高くなります。
- 腸内環境の変化: 抗生物質の服用や腸炎などの病気により、腸内環境が変化すると、ラクターゼの活性が低下することがあります。

腸内環境を整えて、美と健康を手に入れる!最新情報と改善方法を徹底解説
症状

乳製品不耐症の症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 腹痛
- 下痢
- 腹部膨満
- 嘔吐
- ガス
これらの症状は、乳製品を摂取してから数時間から数日で現れます。
対処法

乳製品不耐症の対処法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 乳製品を控える: 乳製品を摂取しなければ、症状が出ることはありません。
- ラクターゼサプリメントを摂取する: ラクターゼサプリメントを摂取することで、乳糖を分解し、症状を軽減することができます。
- 乳糖分解酵素入り乳製品を摂取する: 乳糖分解酵素が入った牛乳やヨーグルトなどの乳製品も販売されています。
乳製品を完全に控えるのは難しい場合も多いので、自分に合った対処法を見つけることが大切です。
乳製品アレルギーとは?

乳製品アレルギーは、乳製品に含まれるたんぱく質などに免疫システムが過剰反応することで起こります。
原因
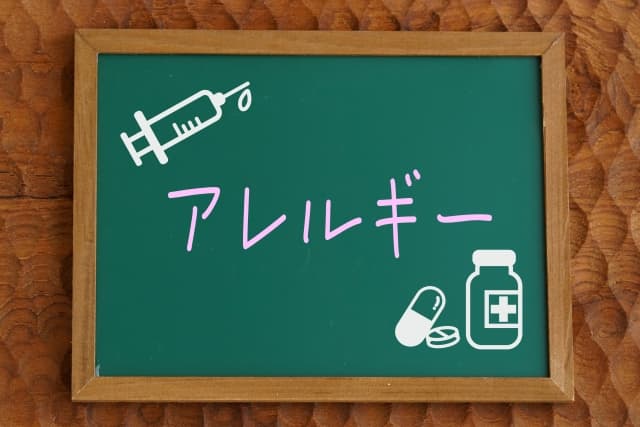
乳製品アレルギーの原因となるたんぱく質としては、カゼイン、β-ラクトグロブリン、α-ラクトアルブミンなどが挙げられます。
乳製品アレルギーは、乳児期に発症することが多く、成長とともに自然治癒するケースもあります。
私の娘も、乳児期に乳製品アレルギーがありました。
2歳前に負荷試験を行い除去解除になりましたが、その後は症状が発現することなく現在に至ります。
中には、大人になって発症することもあります。

症状

乳製品アレルギーの症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 蕁麻疹
- かゆみ
- アナフィラキシー
これらの症状は、乳製品を摂取してから数分~数時間以内に現れます。
重症の場合は、アナフィラキシーを起こし、呼吸困難や血圧低下などの症状が現れる場合もあります。
対処法

乳製品アレルギーの対処法としては、以下のものが挙げられます。
- 乳製品を完全に除去する: 乳製品を摂取しなければ、症状が出ることはありません。
- エピペンを持ち歩く: アナフィラキシーを起こした場合は、エピペンを注射することで症状をを抑えることができます。
乳製品アレルギーは、重症化すると命に関わることもあるため、注意が必要です。

乳製品アレルギーと上手に付き合う:症状、原因、対処法、代替食品まで完全ガイド
乳製品不耐症と乳製品アレルギーの違い

乳製品不耐症と乳製品アレルギーの違いを表にまとめました。
【乳製品不耐症と乳製品アレルギーの比較表】
| 項目 | 乳製品不耐症 | 乳製品アレルギー |
|---|---|---|
| 原因 | ラクターゼの活性が低い | 免疫システムの過剰反応 |
| 症状 | 主に消化器症状(腹痛、下痢、腹部膨満、嘔吐、ガス) | 皮膚症状(じんま疹、かゆみ)、呼吸器症状(喘息、鼻水、アナフィラキシー) |
| 症状の出現時間 | 乳製品を摂取してから数時間~数日 | 乳製品を摂取してから数分~数時間以内 |
| 対処法 | 乳製品を控える、ラクターゼサプリメントを摂取する、乳糖分解酵素入り乳製品を摂取する | 乳製品を完全に除去する、エピペンを持ち歩く |
乳製品不耐症と乳製品アレルギーは、どちらも乳製品を摂取することで起こる症状ですが、原因、症状、対処法が異なります。
- 乳製品不耐症: ラクターゼの活性が低いことが原因で起こる。症状は主に消化器症状で、乳製品を摂取してから数時間から数日で現れる。対処法としては、乳製品を控える、ラクターゼサプリメントを摂取する、乳糖分解酵素入り乳製品を摂取するなどが挙げられる。
- 乳製品アレルギー: 免疫システムの過剰反応が原因で起こる。症状は皮膚症状や呼吸器症状など、より広範囲にわたる。乳製品を摂取してから数分~数時間以内に現れる。対処法としては、乳製品を完全に除去する、エピペンを持ち歩くなどが挙げられる。
乳製品を摂取した後に体調に異変を感じた場合は、医療機関を受診し、適切な診断を受けることが大切です。
